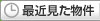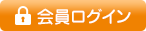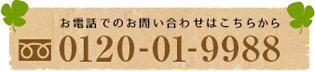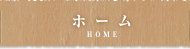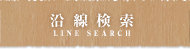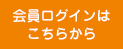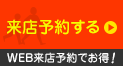築40年以上の住宅を所有されている方のなかには、売却できるのかと不安な方もいらっしゃるでしょう。
昨今は、中古住宅の需要も増えてきているため、築年数が経過している家でも売ることは十分に可能です。
そこで、築40年以上の住宅の売却をご検討中の方に、かつて売れにくいと言われていた理由や放置するリスク、また売却方法についてご紹介します。
築40年以上の住宅が売却しにくいと言われていた理由とは
一般的に築年数が経過している家ほど売れにくいと言われています。
なぜなら、家は築年数が経過するごとに資産価値が減少していき、木造の場合は築20〜25年ほどでゼロとされているからです。
また、築40年以上の家は旧耐震基準で建てられているため、耐震性能が低い可能性があります。
このような理由により、築40年以上経過している家は売れにくいと言われてきました。
しかし、近年では築年数が経過している家でも売れるケースが増えてきています。
それは築年数に関係なく、住宅本来の性能を重視しようとする消費者の意識が変わってきたからです。
また中古住宅を安く購入して、自分の好みにリフォームしたいという方も増えています。
このような理由から、現在では中古住宅が見直されてきています。
築40年以上の住宅を売却せずに放置するリスクとは
築40年以上の家でも前述のとおり需要は見込めますが、そのまま放置しておくのはリスクが大きいと言えます。
まず心配されるのは、倒壊のリスクです。
築年数が経過していれば老朽化は進んでおり、さらに誰も住まずに放置すると老朽化がさらに進むことになります。
また、家を放置し続ければ自治体から「特定空き家」に指定されるリスクもあります。
特定空き家に指定されると、強制処分やその費用負担を強いられることになりかねません。
家を所有している限りは固定資産税などの税金も発生するため、放置するのなら早く売ることを検討したほうが良いでしょう。
築40年以上の住宅を早く売却する方法とは
時間と資金に余裕がある場合は、リフォームをすることで早く売れる可能性が高くなります。
リフォームは家自体の資産価値を高め、買主が見つかりやすくなることにつながるでしょう。
また、解体して更地にしてから売却する方法もあります。
解体費用を負担する必要はありますが、更地にすることですぐに新築を建てることができるので、買主にとってはメリットが大きいです。
また、建物はそのままで土地とともに「古家付き土地」として売り出すことも、早期売却に効果的でしょう。
建物と土地の両方の需要があるため、買主が見つかりやすくなります。
まとめ
築40年以上の住宅が売れにくい理由や放置するリスク、また売却方法についてご紹介しました。
築年数が経過した住宅は、放置することで老朽化が進むなどリスクが大きいです。
そのため、活用予定がない場合はできるだけ早く売却を検討することをおすすめします。
野田市の新築・中古戸建てはひだまりハウス野田店へ!
2,000万円以下の物件をはじめ、お客様に寄り添った豊富な物件情報をご紹介しますので、お気軽にご相談ください!
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
ひだまりハウス野田店 スタッフブログ担当
野田市で不動産を探すならひだまりハウスにおまかせ!新築一戸建て、中古戸建て、ファミリー向けなど豊富な不動産情報を取り扱っています。ブログでは当サイトのユーザーの方に有益な情報をお伝えするため、不動産に関する記事をご提供します。